ビットコインの取引は「トランザクション」と呼ばれ、単なる送金データのやり取りではありません。
過去の取引情報を参照しながら新しい取引が連鎖的に積み重なることで、安全かつ透明な仕組みを実現しています。
しかし、その仕組みは複雑で、初心者には理解が難しい部分も多いのが現状です。
この記事では、ビットコインのトランザクションがどのように成り立っているのか、なぜ署名が必要なのか、そして手数料や検証の仕組みまで、わかりやすく解説します。
ビットコインの基礎をしっかり理解したい方におすすめの内容です。
- ビットコインのトランザクションの基本構造と連鎖構造の仕組み
- TxIn(入力)とTxOut(出力)の役割と関係性
- 秘密鍵による署名がトランザクションの安全性を支える理由
- トランザクション手数料の計算方法と重要性
- トランザクション検証の負荷が高い理由とその背景

今回の記事ではビットコインのトランザクションについてご紹介していくよ!
トランザクションは「支払元」と「支払先」で構成される
ビットコインの取引を支える「トランザクション(transaction)」とは何か。その基本構造を理解することは、ブロックチェーンの仕組みを正しく捉えるうえで非常に重要です。
この記事では、ビットコインにおけるトランザクションの仕組みを「TxIn(支払元)」と「TxOut(支払先)」の視点から解説します。
トランザクションとは?
ビットコインにおけるトランザクションとは、ビットコインの送金情報を記録したデータ構造です。
ある人が他の誰かにビットコインを送るとき、この取引が1つのトランザクションとして生成され、ブロックに取り込まれてブロックチェーンに記録されます。
TxIn:支払元の構造と役割
トランザクションの入力(TxIn: Transaction Input)は、「どこからビットコインを得たのか」を示す情報です。
特徴的なのは、アドレスや金額が直接書かれていない点です。
TxInには、以下の情報が記録されています
- 以前のトランザクションのID(取引ID)
- そのトランザクションの中のどの出力(TxOut)を使うのかというインデックス番号
- 使用権を証明する署名(秘密鍵による)
つまり、「このビットコインを以前誰から受け取ったのか」を過去のトランザクションを参照することで示す仕組みになっています。
TxOut:支払先の構造と役割
出力(TxOut: Transaction Output)は、「誰にどれだけビットコインを送るのか」を示す部分です。
TxOutには、以下の情報が記録されています
- ビットコインの数量
- 受取人のビットコインアドレス(実際にはスクリプト形式)
トランザクションは1つ以上のTxOutを含むことができます。
つまり、複数人に同時送金することも可能です。
手数料の仕組み
TxIn(支払元)の合計金額からTxOut(支払先)の合計金額を引いた差額がマイナー(採掘者)の報酬となる手数料になります。
この手数料はトランザクションごとに自由に設定できます。
トランザクション解析の難しさ
TxInが過去のTxOutを参照する構造であるため、支払元の金額を確認するには、ブロックチェーン上に存在する無数のトランザクションの中から該当するものを探し出す必要があります。
この構造のため、独自にビットコインノードやウォレットソフトを開発する際は、「未使用のTxOut(UTXO)を効率的に管理する仕組み」が極めて重要です。
また、二重支払い(ダブルスペンド)を防ぐための検証処理も慎重に設計しなければなりません。
ビットコインのトランザクションは、「支払元(TxIn)」と「支払先(TxOut)」のセットで構成されることで、完全な取引の記録を実現しています。
この構造によって透明性・追跡性・改ざん耐性を確保しているのです。
一見複雑に見える仕組みですが、根本を理解すればビットコインやその他のブロックチェーン技術への理解が大きく深まるでしょう。
TxInの中身には金額もアドレスも書かれていない?
実はTxInには、送金元のアドレスや金額は直接記載されていません。記録されているのは次の2つだけです。
つまり、TxIn は「どのコインを使っているか」という参照情報しか持っていません。
そのため、実際の金額やアドレスを確認するには、参照先のTxOutの情報をさかのぼって確認する必要があります。
これは、ビットコインが UTXO(Unspent Transaction Output)モデルを採用しているからです。
UTXOモデルでは、「未使用の出力(コイン)」が通貨残高として扱われます。
トランザクションは、過去の出力を「使う」と宣言することで実行されます。
TxInは秘密鍵で署名されている
ビットコインのトランザクションで最も重要な要素のひとつが「署名」です。
とくにTxIn(トランザクション入力)の部分では、秘密鍵による署名が不可欠です。では、なぜ署名が必要なのでしょうか?
所有者であることを証明するため
ビットコインは物理的なコインが存在するわけではなく、「誰がどのコインを持っているか」はブロックチェーン上の記録だけで管理されています。
このとき、「このビットコインを使う権利があるのは自分ですよ」と証明する必要があります。
ここで使われるのが「秘密鍵によるデジタル署名」です。
秘密鍵によるデジタル署名
- TxInで参照している過去のトランザクション(UTXO)を「使う」と宣言
- その内容を、自分だけが持つ秘密鍵で署名
- 他の人(ノードやマイナー)が、対応する公開鍵を使って署名が正しいか検証
この仕組みによって、「そのコインの本当の持ち主だけが署名できる」ことが保証され、不正な使用やなりすましを防げるのです。
金額やアドレスは署名されていない?
TxInの中には、送金金額や送金先のアドレスといった情報は含まれていません。
そうした情報はTxOut側に記録されています。
では、TxInで署名されているのは何かというと、「自分が参照するUTXOの情報」「これから新しく作るトランザクション全体の内容(TxOut含む)」です。
つまり、「どこから」コインを使って、「どこに送るか」という一連の動きをまとめて署名しているのです。
これにより、トランザクションの改ざんも不可能になります。
秘密鍵と公開鍵の役割
- 秘密鍵:ユーザーだけが持っている「サインペン」。トランザクションに署名するために使う。
- 公開鍵:ブロックチェーン上にある。誰でも検証できる「照合のテンプレート」。
このペアによって、「本人だけがコインを使える」という所有権の仕組みが成立しています。
ビットコインにおける「所有者の証明」は、秘密鍵による署名付きのTxInによって実現されています。
この署名があることで、第三者が勝手にコインを使うことができなくなり、ブロックチェーン上の全取引の正当性が担保されるのです。
「TxInはただの入力欄ではなく、所有者を証明するデジタル署名付きの証拠書類である」と覚えておくとよいでしょう。
TxInとTxOutの差が「手数料」になる
ビットコインのトランザクション(取引)では、「支払元(TxIn)」と「支払先(TxOut)」の合計額に差がある場合、その差額はネットワークのマイナー(採掘者)に支払われる「手数料(Fee)」として扱われます。
これは、銀行などのように明示的な送金手数料を別途指定するのではなく、TxInの合計金額からTxOutの合計金額を差し引いた分が自動的に手数料になるという仕組みです。
たとえば、以下のようなケースを考えてみましょう。
- TxIn(支払元)合計:1.0 BTC
- TxOut(支払先)合計:0.98 BTC
この場合、0.02 BTC が手数料としてマイナーに支払われることになります。
手数料は高ければ高いほど、トランザクションがブロックに早く取り込まれる可能性が高くなります。
なぜなら、マイナーは手数料の高いトランザクションを優先的に処理したいからです。
逆に、手数料をあまりにも低く設定すると、なかなかブロックに取り込まれず、送金が長時間未処理のままになるリスクもあります。
このように、手数料はネットワークの健全な動作と取引の迅速な処理に関わる重要な要素です。
送金時には、ネットワークの混雑状況に応じて適切な手数料を意識する必要があります。
トランザクションの検証が重い処理になる理由
ビットコインにおけるトランザクション(取引)の検証は、単なる数値チェックではなく、暗号技術に基づく複雑な計算を伴う処理です。
マイナーやノードは、新しいトランザクションがネットワーク上に流れた際、以下のような検証を行います。
- TxInのUTXO参照が正しいか
TxInで指定されている「未使用トランザクション出力(UTXO)」が本当に存在しているか、すでに他のトランザクションで使われていないかをチェックします。これは、ダブルスペンド(二重支出)を防ぐために不可欠な処理です。 - 秘密鍵による署名の正当性検証
TxInには送金者の署名が含まれており、その署名が対応する公開鍵(アドレス)によって正当であるかどうか、つまり本当にそのビットコインの所有者が署名したのかを検証します。これにはECDSA(楕円曲線暗号)という複雑な計算が必要です。 - TxInとTxOutの整合性チェック
合計金額が過不足ないか、出力がマイナスになっていないか、スクリプトが適切かなど、ルール違反がないかの検証も行われます。
これらすべての検証はノードやマイナーによって実行されるため、トランザクション数が増えるほど計算負荷が高まり、CPUやメモリに大きな負担がかかることになります。
特にブロックに多数のトランザクションが詰め込まれると、その検証は膨大な処理量になります。
そのため、検証作業を高速にこなせるよう、フルノードには高性能なハードウェアが求められ、ソフトウェアも最適化され続けています。
二重払いの防止はどうしている?
ビットコインにおける最大の課題の一つが「二重払い(ダブルスペンド)」の防止です。
二重払いとは、同じビットコインを複数回使ってしまう不正行為のことを指します。
このように、ビットコインの分散型ネットワークは、トランザクションの「UTXOの一度だけ使用」というルールを基盤にして、二重払いを技術的に防止しています。
これにより、中央管理者なしでも信頼性の高い通貨システムが実現できているのです。
まとめ|ビットコインのトランザクションは「連鎖構造」で成り立つ
ビットコインのトランザクションは「連鎖構造」と呼ばれる仕組みで成り立っています。
具体的には、各トランザクションの入力(TxIn)が過去の取引の出力(TxOut)を参照することで、新しい取引が連続的につながっているのです。
この構造により、すべての取引はブロックチェーン上で透明かつ追跡可能となり、不正や二重払いを防止しています。
また、TxInには所有者の秘密鍵による署名が含まれており、正当な所有者が送金していることを証明します。
さらに、TxInの合計額からTxOutの合計額を差し引いた差額は手数料としてマイナーに支払われ、ネットワークの維持や取引処理のインセンティブとなっています。
一方で、トランザクションの検証には過去の膨大な取引データを参照し、署名の正当性を確認する必要があるため、計算負荷が高くなりますが、この負荷こそがビットコインのセキュリティと信頼性を支える重要な要素となっています。
こうした連鎖的かつ厳格な仕組みによって、ビットコインは中央管理者なしで安全な価値の移転を実現しているのです。
その他のおすすめ記事

最後までご覧いただき、ありがとうございました!私個人に対する質問やご相談は@XAozameXのDMまでご連絡ください。

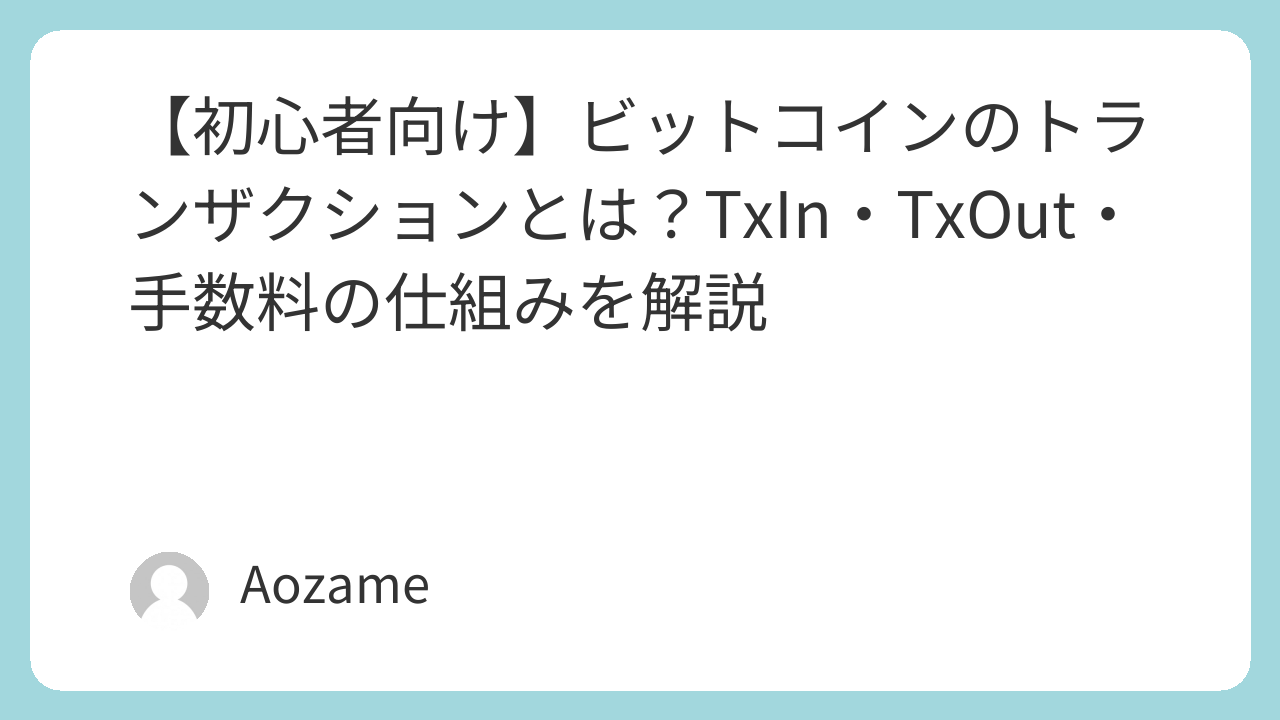
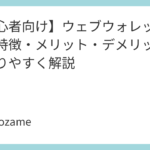
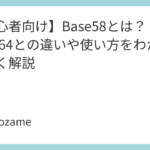
コメント