暗号通貨(英:Cryptocurrency)とは、暗号技術を用いて取引の安全性を確保しているデジタル通貨の総称です。
日本では「仮想通貨」という呼び名が一般的ですが、海外では「暗号通貨(Cryptocurrency)」という表現がよく使われています。
たとえば、代表的な暗号通貨であるビットコイン(Bitcoin)は、インターネット上で誰でも自由に送金や受取ができるように設計されており、銀行や政府のような中央管理者を必要としません。
- 暗号通貨(Cryptocurrency)とは何か、その定義と特徴
- 仮想通貨との違いと呼び方の使い分け
- 暗号通貨の安全性を支える仕組み(公開鍵暗号・ハッシュ・電子署名)
- SuicaやPayPayなどの電子マネーと暗号通貨の違い
- 暗号通貨が非中央集権かつ安全なデジタル通貨である理由

今回の記事では暗号通貨(Cryptocurrency)についてご紹介していくよ!
仮想通貨との違いはあるの?
基本的には、仮想通貨と暗号通貨はほぼ同じ意味で使われています。しかし、厳密に言えば以下のような違いがあります。
| 用語 | 主な使われ方 | 例 |
|---|---|---|
| 暗号通貨 | 暗号技術を使った通貨という技術的な側面の強調 | Cryptocurrency、Bitcoin など |
| 仮想通貨 | 法律や経済的な観点からの呼称 | 金融庁・資金決済法での用語 |
暗号通貨(Cryptocurrency)とは?
- 暗号技術(公開鍵暗号、ハッシュ、電子署名など)を使ったデジタル通貨を意味します。
- ブロックチェーン技術に基づくものが多く、非中央集権的(管理者がいない)な取引システムが基本です。
- 海外ではこの「Cryptocurrency(暗号通貨)」という呼び方が一般的です。
仮想通貨とは?
- 日本の法律(資金決済法など)では「仮想通貨」という言葉が使われています。
- 暗号技術を使っているかどうかに関係なく、法律的に定義された交換手段や資産的価値を含む表現です。
- 例:金融庁や暗号資産交換業者が扱う通貨は「仮想通貨」と表記されることが多いです。
つまり、「仮想通貨」は法律上の呼び名であり、「暗号通貨」は技術に焦点を当てた呼び名と考えるとわかりやすいです。
2020年から「暗号資産(Crypto-assets)」が正式名称に?
日本では2020年に法改正が行われ、「仮想通貨」→「暗号資産」と呼称が変更されました。
これは、仮想通貨という言葉が曖昧で投資家を誤解させるという理由によるもので、より資産性・金融商品としての側面を明確にするためです。
暗号通貨の仕組み|なぜ「安全」なのか?
暗号通貨は、第三者(銀行や企業)に依存せずに、安全な取引ができる仕組みを持っています。
その中核となっているのが、暗号技術とブロックチェーン技術です。
ここでは、暗号通貨がなぜ「安全」と言われるのか、3つの主要な技術に分けて解説します。
| 技術名 | 主な役割 |
|---|---|
| 公開鍵暗号 | 本人確認・なりすまし防止 |
| ハッシュ関数 | 改ざん防止・データ整合性の確認 |
| 電子署名 | 取引の正当性を証明 |
| ブロックチェーン | 不正履歴を作れない仕組み |
公開鍵暗号方式(こうかいかぎあんごう)
公開鍵暗号とは、2つの鍵(公開鍵と秘密鍵)を使って安全な通信を行う技術です。
秘密鍵と公開鍵の違いとは?
- 秘密鍵:自分だけが知っている鍵。これで「署名」します。
- 公開鍵:誰でも見られる鍵。秘密鍵で署名されたものを「検証」するために使います。
暗号通貨では、取引を行うときにこの仕組みを使って本人確認と改ざん防止をしています。
たとえば、「自分のウォレットから誰かにビットコインを送る」という行為は、秘密鍵で署名されたメッセージをネットワークに送信することです。
他人は秘密鍵を知らないため、なりすましはできません。
ハッシュ関数(Hash Function)
ハッシュ関数とは、あるデータを固定長の文字列に変換する関数です。
一方向の関数であり、「元に戻すことができない」のが特徴です。
- 各取引データやブロックの中身をハッシュ関数で変換
- データの改ざんがあると、生成されるハッシュ値が完全に変わる
- 少しでも内容をいじると違う結果になるため、改ざんの検出が即座に可能
これにより、取引の履歴(ブロックチェーン)を改ざんできない形で永久に記録できます。
電子署名
上記2つを組み合わせた技術。自分が行った取引であることを証明する手段として利用されます。
これにより、ネットワーク上のノード(参加者全員)が「この取引は正しい」と判断でき、信頼性のある取引が成立します。
SuicaやPayPayは暗号通貨じゃない?
「じゃあSuicaやPayPayのような電子マネーも暗号通貨なのでは?」と疑問に思うかもしれませんが、電子マネーと暗号通貨はまったくの別物です。
| 比較項目 | 暗号通貨(ビットコインなど) | 電子マネー(Suica、PayPayなど) |
|---|---|---|
| 管理者 | なし(非中央集権) | あり(企業が管理) |
| 通貨の発行・管理 | オープンソースのプロトコルに基づく | 企業がチャージ残高を発行・管理 |
| 送金の仕組み | ブロックチェーンによる分散型台帳 | 中央サーバーによる記録 |
| 匿名性 | あり(ウォレットアドレスで管理) | 基本的に個人情報や銀行口座と連携 |
| 利用目的 | グローバルな価値交換・投資 | 国内の決済・ポイント還元など |
| 技術的基盤 | 暗号技術・分散ネットワーク | クラウド・自社サーバー・通常のデータベース |
SuicaのようなICカード型の電子マネーは、「前払式支払手段」と呼ばれ、法律上も暗号通貨(仮想通貨)とは別枠で扱われています。
つまり、通貨ではなく「企業の発行するポイントや証票」に近い存在です。
暗号通貨は、ブロックチェーン技術を用いた非中央集権型の通貨システムです。
誰もがネットワークを検証し合うことで成り立っています。
電子マネーは、特定の企業や団体が中央で一元管理している決済手段です。
ユーザーの残高や取引履歴もすべてその企業の管理下にあります。
SuicaやPayPayはキャッシュレス社会を支える便利なツールですが、「ブロックチェーン」や「暗号技術」によって価値を支えているわけではなく、暗号通貨とはまったく別のカテゴリです。
暗号通貨のように「非中央集権」「改ざん不可能な取引履歴」「世界中での自由な送金」などの特徴を持っているわけではありません。
まとめ|暗号通貨は「非中央集権で安全なデジタル通貨」
暗号通貨(Cryptocurrency)は、中央管理者が存在しない非中央集権型の安全なデジタル通貨です。
ブロックチェーン技術を用いて多くの参加者が取引を検証・記録するため、一箇所での改ざんや不正が極めて困難です。
公開鍵暗号や電子署名、ハッシュ関数といった高度な暗号技術により、不正取引やなりすましを防止し、取引の透明性と信頼性を確保しています。
日本では「仮想通貨」や「暗号資産」とも呼ばれ、法的な位置づけが整備されつつあります。
一方で、SuicaやPayPayのような電子マネーは企業が中央で管理する決済手段であり、前払い式のサービスとして暗号通貨とは仕組みも目的も異なります。
暗号通貨は金融や価値交換のあり方を革新する可能性を持ち、今後も技術進化と法整備が進むことで私たちの生活に大きな影響を与えるでしょう。
その他のおすすめ記事

最後までご覧いただき、ありがとうございました!私個人に対する質問やご相談は@XAozameXのDMまでご連絡ください。

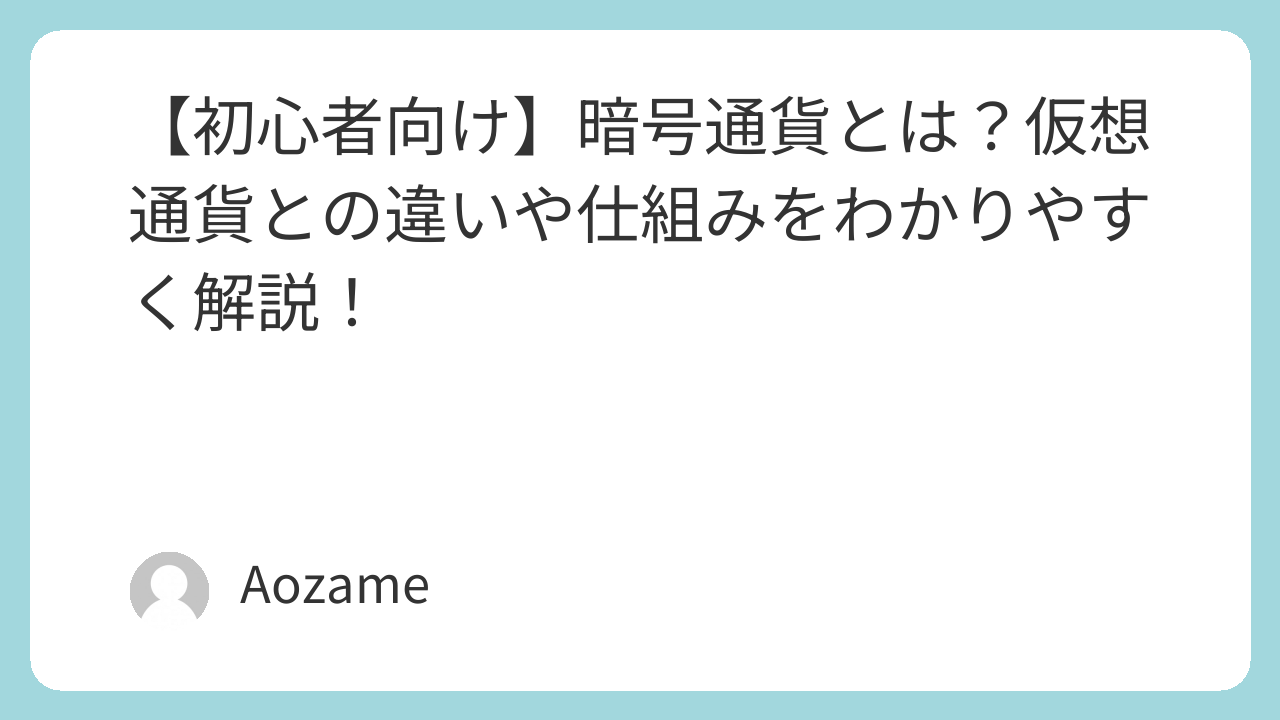
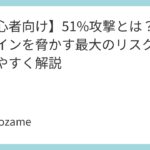
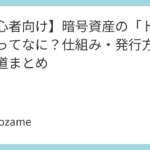
コメント